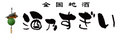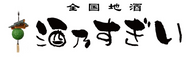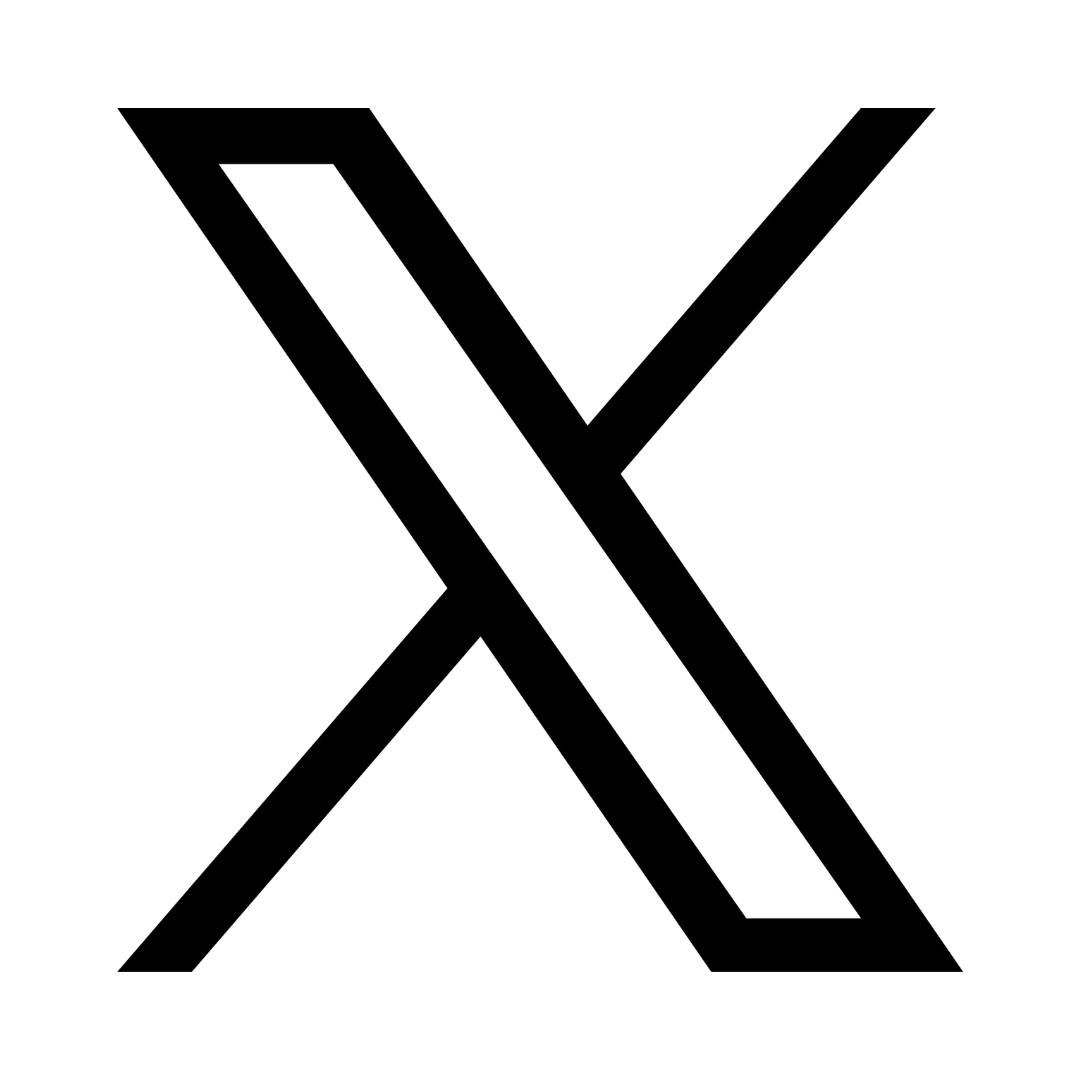山廃(やまはい)、生酛(きもと)を語る前に少し整理しましょう
日本酒のアルコールを造る工程:酵母を育てる「酛」(酒母)造りには、速醸酛、生酛の二種類があります。
速醸酛
現在ほとんどの酒蔵が行ってる手法で、市販の乳酸と培養酵母を加え、2週間あまりでできる速醸酛
透明感があり淡麗でスッキリした酒質に適しています。
生酛
昔ながらの手作業で、蔵に住み着いている乳酸と天然酵母を加え、4週間かけて造り上げる生酛
自然界の味わいが活きており、コクがあって、複雑で濃厚な酒質になります。
(乳酸やアミノ酸が多いので、お燗向きでもあります)
 ※伝統生酛造りを守り続ける大七酒造 福島県
※伝統生酛造りを守り続ける大七酒造 福島県
-山廃、生酛の関係性-
生酛造りの工程に(米を溶かす時間を早めるために、カイを使い米を擂り潰す作業)を「山卸」と呼びます
その「山卸」の工程を廃止したつくりを「山廃」と呼びます。

-生酛-
「生酛系酒母という自然の乳酸菌の力で雑菌を排除して、酵母が活動しやすい状態をつくり、アルコール発酵を促進する。また、山卸しという米を擂り潰す作業を行う伝統的な醸造方法」わかりやすく言うと、「自然の力を活用した、昔ながらの日本酒の造り方、酒造りの原点と言える製法」です。しかしながら生酛造りは通常の倍以上の時間と手間がかかり、安定的に行うことも極めて難しいため、全国千数百蔵の中でこれを伝承するのは、菊正宗を含めてわずか数蔵。手から手へと受け継がれてきた生酛造りの技が今若い蔵元達からは、見直されています。
-山廃-
生酛と山廃はどちらも同じ酛づくりの手法をベースにしていますが、
技術革新が進み、米をわざわざ擂り潰さなくても、材料の投入順序を変えることで、山卸の作業を省いても、変わらない「生酛」の味わいを造り出すことができるようになりました。それよりも酒母が仕上がってからの醪の育成や搾ったあとの扱いによって変化する部分のほうが大きいとされています。
生酛仕込みに比べ山廃仕込みの日本酒の方がマイルドな味わいに仕上がります。